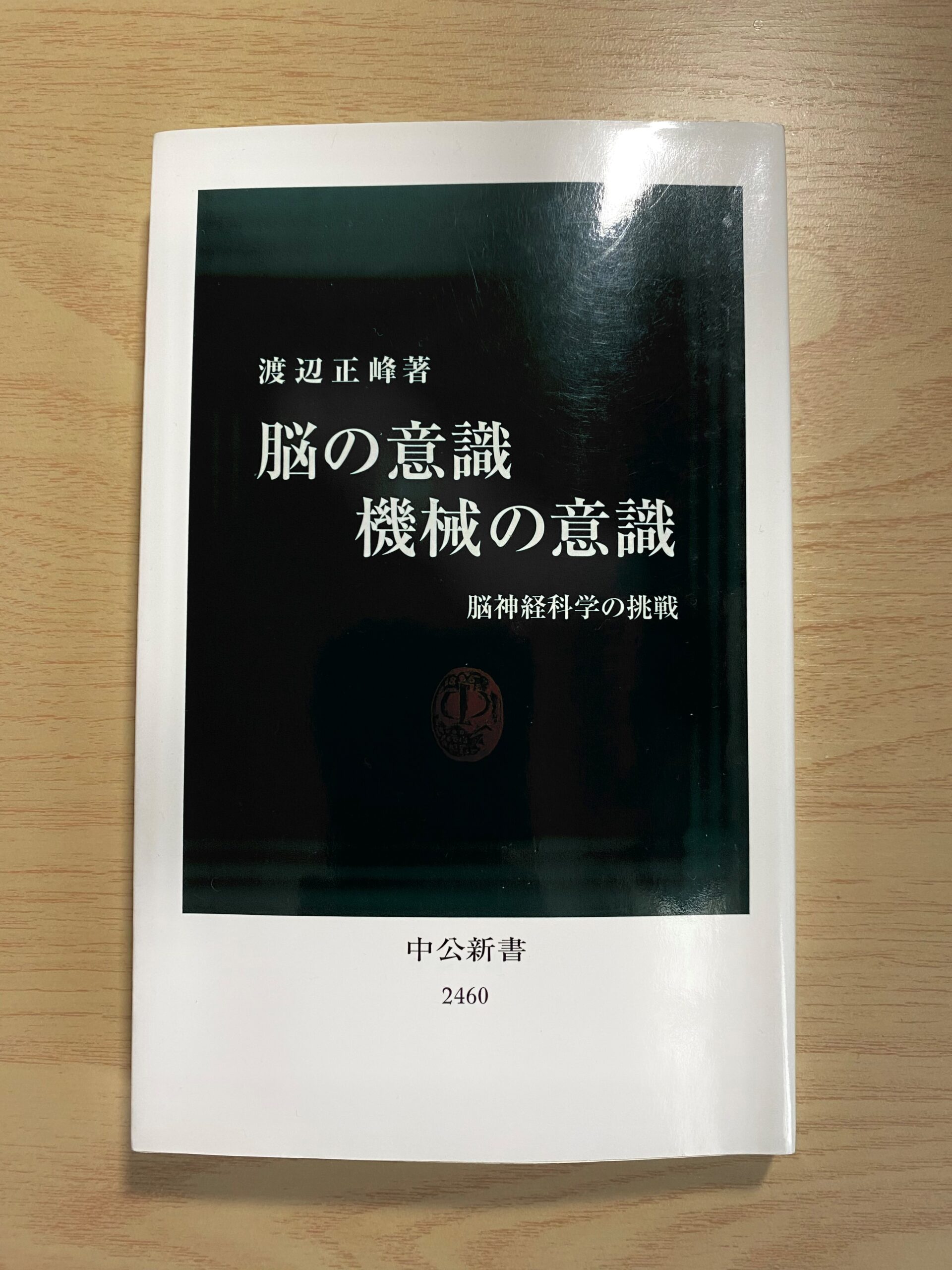「脳の意識 機械の意識―脳神経科学の挑戦―」渡辺正峰 を読んだので、要約して紹介します。
・脳の仕組みを知りたい人
・機械に脳のデータを移したい人
・意識とは何かを考えたい人
本の概要
もしも自身の意識を機械に移植できるとしたら、あなたはそれを選択しますか?
健康な肉体で生きているうちは、容易に選択できないかもしれません。
一方で死の淵に面していたなら、移植を選択する人の数は増えるかもしれません。
しかしながら現時点では、意識の原理自体が全く分かっていません。
意識の科学は未だ普遍的な道筋がなく、研究者によって異なる多くの立場が存在しています。
そもそも意識の何が問題であり、どこから手をつけていくべきなのかということも、科学者や哲学者の間で意見が分かれています。
しかし、人間の意識を機械に移植することは、遠くない未来に実現すると著者は述べます。
著者の専門は脳神経科学で、日々マウスによる実験を重ね、意識にまつわる研究をしています。
本書を読むことで、以下のようなことが学べます。
- 「意識」とは何を指しているのか
- 脳内のニューロンの活動について
- 意識を解明するための研究方法
- 意識の正体に関する様々な考察
- 人間の身体から機械に意識を移す方法
以下、本書から印象に残った部分を要約しました。
我思う、ゆえに我あり
「我思う、ゆえに我あり」という有名な命題を残した近代科学の父、ルネ・デカルト(1596~1650)は、
真理の追究のために、全てを疑うことから始めました。
デカルトは始めに目に見えるもの、耳に聞こえるものなどの自身の感覚を疑いました。
なぜなら錯覚や幻覚などは、現実の事象と食い違うことがよくあるからです。
また、自身がある瞬間に目覚めているのかどうかも疑いました。
なぜなら夢の途中で夢だと気づくことは稀なことだからです。
このようにして疑わしきものを一つずつ排除していきました。
すると最後に残ったものが、デカルト自身の思考、すなわち意識でした。
デカルトのいう「我」が、本書の中で対象とする意識です。
クオリア問題
私たちにあって、コンピュータなどの機械にないものは「クオリア」です。
ものを見る、音を聴く、手で触れるなどの感覚意識体験を「クオリア」といいます。
カメラの場合は画像を処理しそれを記録しているだけなので、人間が「見えて」いることとは本質的に異なるのです。
私たちは世界そのものの姿を見ている訳ではありません。
私たちは色の付いた世界で生きているように感じますが、実際の世界には色は付いていません。
色はあくまで脳が創り出したものにすぎず、色の付いた世界は実際には電磁波が飛び交う世界です。
そのため私たちが見ている世界は、眼球からの視覚情報を元に脳が都合良く編集した世界といえます。
私たちにとって世界が見えていることは当たり前過ぎるあまり、日常生活でこのことを意識することはほとんどないでしょう。
つまり我々の視覚世界は脳の創り物にすぎないのです。
意識
「サーモスタットに意識は宿るか」
一見、荒唐無稽に思えるこの問いかけについて、意識の専門家たちは真剣に議論を繰り返しています。
サーモスタットは、室温に合わせて冷暖房の出力を調整するデバイスです。
熱膨張の度合いの異なる2枚の薄い金属片を重ね合わせると、室温に応じて変形します。
それをヒーターのスイッチに用いることで、寒いときには片側に曲がってスイッチをオンにし、温かくなったときには反対側に曲がってスイッチをオフにします。
サーモスタットに意識が宿ると主張するのは、意識の哲学の第一人者、デイヴィット・チャーマーズです。
彼の哲学の中心にあるものは、「すべての情報は、客観的側面と主観的側面の両者を併せもつ」という、「情報の二相理論」です。
彼の理論に従うと、室温という情報を自らの曲がり具合として保持するサーモスタットには意識が宿るといえるのです。
しかしながら意識といっても、私たち人間が感じるような「暑い・寒い」とはまったく異なる代物である可能性が高いでしょう。
フェーディング・クオリア
意識の宿る機械を作ることはできるでしょうか。
この問いを考えるに当たり、「フェーディング・クオリア」という思考実験があります。
まずはじめに、生体のニューロンを一つだけ人工のニューロンに置き換えます。
この人工ニューロンは生体のニューロンと寸分違わず、さらに元の神経の配線も再現できているとします。
そうなると、他の生体ニューロンは人工ニューロンに置き換わったことに気がつかず、以前と全く同じ働きを続けるでしょう。
では、生体ニューロンを一つずつ人工ニューロンへ置き換えていった場合には何が起こるでしょうか。
最終的に生体ニューロンは全て人工ニューロンに置き換わりますが、脳の神経回路網の振る舞いは生体ニューロンで構成されていたときと変わりません。
つまり、脳が人工のものに全て置き換わったとしても意識は消失せず、人工物にも意識が宿ると結論づけられるのです。
生体の脳に宿っていた意識を機械の中に移動させることは夢ではないと言えます。
機械脳半球との接続
生体脳の意識を機械の中に移動させるには、具体的にどんな方法を取れば良いのでしょうか。
その方法について著者は、片方の脳半球を機械の脳半球に置き換えることで意識を移動できると考えています。
簡単に手順を説明します。
まず右脳と左脳を分離する手術を行ない、意識を2つに分割します。
そして片方の脳半球(生体脳)と脳となる機械(機械脳)を接続します。
その後数時間から数年間、生体脳と機械脳を接続し続けて生活します。
すると徐々に生体脳の意識と機械脳の意識が統合されていきます。
その過程が終了し、機械脳に感覚意識体験(クオリア)が形成されていれば、機械に意識を移植できたと言えます。
しかし意識が移植できた後は、記憶を移植しなければなりません。
脳半球と機械半球が接続されている間の記憶は蓄えることができると考えられていますが、接続する前の過去の記憶を移すことは難しいだろうと想定されています。
しかしそういった想定に対し、著者は前向きに捉えています。
著者は「過去の記憶を思い出す」という脳活動を機械脳と共有することで、過去の記憶を移植できると考えています。
最終的にはこの技術によって、意識を永遠に生かし続けることもできるようになると言います。
まとめ
「脳の意識 機械の意識―脳神経科学の挑戦―」渡辺正峰 を要約して紹介しました。
本書では脳を研究する手法が丁寧に解説されており、意識研究の現状を知ることが出来ます。
そして脳が以外にも単純な作りでできていることが理解できると思います。
しかしながら単純な作りであるにも関わらず、脳に意識が宿る仕組みを特定することはできていないのです。
脳のどこを探しても見つからない意識がどうやって生まれるのかについては多様な考察がされており、知的好奇心を存分に刺激します。
そして本書の最後には、脳と機械を接続して意識を移動させる技術が実現可能なものとして紹介されています。
著者はこの技術によって、自身の意識を永遠に生き続けさせようと本気で考えています。
本書を読み終えたときには、SFで見た電脳世界はもはや夢ではないことを実感できるでしょう。
身体に宿る意識を機械に移動できる未来はすぐ近くにあるかもしれません。
以上、村崎でした!